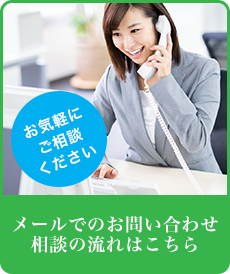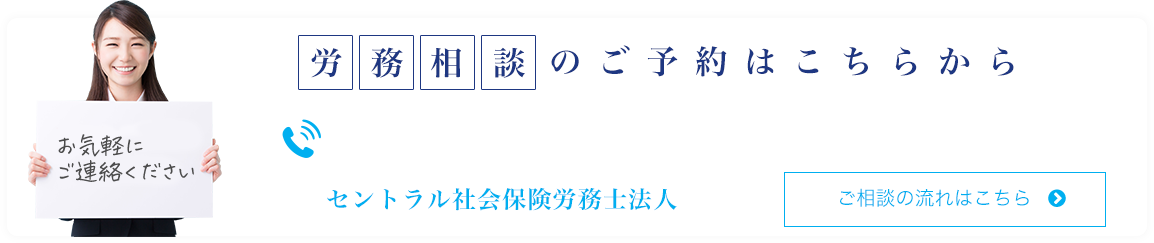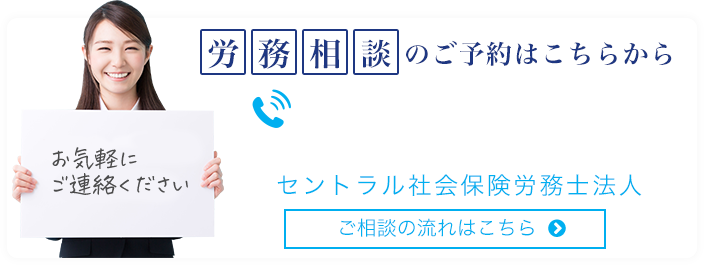「経営リスク削減のためにも、定着率向上のためにも労務リスクを削減したいが、何から手をつければいいかわからない」、「働き方改革関連法、その他労働法の改正に対応できているか不安」という経営者・人事労務担当者の方はまずは「労務監査」で現状を可視化することを推奨いたします。
問題社員の改善指導方法とは?注意点やリスクを社労士が解説!
問題社員への対応は多くの企業が直面する重要な課題です。適切な改善指導を行うことで、社員の成長を促し、健全な職場環境を維持することが可能になります。しかし、その実施には注意点やリスクも伴います。本コラムでは、問題社員の改善指導方法について、その類型から具体的な流れ、注意点、そして事例までを社労士の視点から解説します。
改善指導が必要な問題社員の主な類型
改善指導が必要となる問題社員には、いくつかの典型的な類型があります。それぞれの特性を理解し、適切なアプローチをとることが重要です。
能力不足(職務遂行能力がない)
与えられた業務を期日までに完了できない、同じミスを繰り返すなど、業務遂行能力が期待される水準に達していない社員です。特に中途採用の場合、入社時の期待能力と実際のパフォーマンスに乖離があるケースも見られます。
協調性がない・上司、同僚、取引先と円滑に仕事ができずトラブルを起こす
チームワークを乱したり、周囲とのコミュニケーションが円滑に進まず、人間関係のトラブルを頻繁に引き起こす社員です。ハラスメント行為や、嘘、暴言などもこれに該当します。
無断欠勤、遅刻早退など勤怠不良
正当な理由なく遅刻、早退、無断欠勤を繰り返すなど、基本的な勤怠ルールを守らない社員です。これは職場の秩序を乱し、周囲の業務にも影響を与えます。
会社に批判的・方針に従わないなど反抗的態度で秩序を乱す
会社の指示や命令に従わない、批判的な言動を繰り返すなど、反抗的な態度で職場の秩序を乱す社員です。業務命令違反は重大な問題行為と見なされます。
なぜ改善指導が必要か
問題社員への改善指導は、単に個人の行動を正すだけでなく、企業全体にとって不可欠な取り組みです。
健全な職場環境の維持
問題社員を放置することは、他の真面目な社員のモチベーション低下や不満、不信感を招き、結果として職場の雰囲気を悪化させ、生産性にも悪影響を及ぼします。
法的リスクの低減
将来的に解雇などの厳しい措置を検討する場合、適切な改善指導と証拠の記録がなければ、不当解雇として訴訟に発展するリスクが高まります。裁判所は、会社が社員に改善の機会を十分に与えたかを重視します。
社員の成長と企業の発展
改善指導は、社員が自身の問題点を自覚し、成長するための機会でもあります。問題が改善されれば、社員は戦力となり、企業の発展に貢献することができます。
改善指導の流れ
問題社員への改善指導は、慎重かつ段階的に進める必要があります。
問題の把握と事実確認
具体的な問題行動の内容を客観的に把握し、発生日時、場所、関係者の証言、業務への影響などを詳細に記録します。主観的な評価ではなく、客観的な事実に基づいた記録が重要です。
口頭での注意・指導
初期段階では、具体的な問題行動を指摘し、改善を促す口頭での注意を行います。感情的にならず、冷静に事実と改善点を伝えます。
書面での注意・指導
口頭指導で改善が見られない場合や、問題の程度が大きい場合は、書面による指導に移行します。指導書には、問題行動の具体的内容、会社のルールとの関連、今後の期待や指導内容、再発時の対応方針(懲戒の可能性など)を明記し、本人に受領の署名を求めると良いでしょう。
面談の実施
定期的な面談を通じて、問題行動の改善状況を継続的にモニタリングし、フィードバックやサポートを提供します。面談は冷静かつ客観的に行い、必要に応じて上司や人事担当者など第三者を同席させることも有効です。社員自身の自己評価や、指導プロセスに対する意見を聞くことも重要です。
改善計画の策定と実行
社員自身に改善策を提示させ、具体的な改善計画を作成します。計画には、問題の特定、改善のためのステップ、期限の設定、評価方法を明確に盛り込み、会社は改善に向けたフォローアップを行います。
人事処分の検討・実施
度重なる指導にもかかわらず改善が見られない場合は、就業規則に基づき、譴責、減給、出勤停止などの懲戒処分を検討します。懲戒処分は段階的に重くしていくのが原則です。
最終的な措置(退職勧奨・解雇)
あらゆる指導や処分を経ても改善が見られず、雇用維持が困難な場合は、退職勧奨や最終的な手段として解雇を検討することになります。この場合も、これまでの指導の記録が重要な証拠となります。
改善して欲しい行動・問題行動の記録のポイント
記録は、改善指導の根拠となり、万が一のトラブルの際に会社の正当性を証明するための重要な証拠となります。
客観的な事実を具体的に記録する
「いつも遅刻している」ではなく、「〇月〇日午前9時の会議に15分遅刻した」のように、日時、場所、具体的な行動、業務への具体的な影響(例:顧客対応の不手際により〇〇万円の契約損失が発生した)を記録します。
主観や意見を混同しない
記録は事実に基づき、記録者の主観や感情を排除します。
指導時の社員の反応や態度も記録する
指導に対してどのような反応を示したか、改善の意思が見られたかなども記録しておくと良いでしょう。
定期的にレビューし、一元管理する
エクセル表などを用いて一貫性のあるフォーマットで記録し、定期的に内容を確認することで、問題行動の傾向や指導の効果を把握しやすくなります。
改善指導の実施のポイント
効果的な改善指導を行うためには、いくつかのポイントがあります。
期待する行動や業績の基準を明確に伝える
社員が何を改善すべきか、具体的に何を期待されているのかを明確に伝えます。曖昧な表現は避け、「誰が見ても同じ解釈になるか」という視点で伝達します。
公平かつ一貫性のある対応
特定の社員だけをターゲットにせず、全ての社員に対して一貫したルールを適用します。
感情的にならず、冷静に対応する
指導は感情的にならず、あくまで業務として冷静に行います。人格否定につながるような言動は避け、パワハラと受け取られないよう細心の注意を払います。
就業規則を有効活用する
就業規則に遅刻・欠勤、勤務態度、懲戒処分に関するルールを明確に定め、従業員に周知徹底しておくことが重要です。
専門家への相談を検討する
問題社員への対応は法的な知識が必要となる場面が多くあります。社会保険労務士や弁護士に相談することで、適切な指導の流れや記録方法、リスク回避に関する専門的なアドバイスを得られます。
改善指導の対応事例
当法人がサポートさせていただいた問題社員対応の解決事例はこちらから
まとめ
問題社員への改善指導は、企業経営において避けて通れない重要なプロセスです。感情的にならず、客観的な事実に基づき、段階的かつ丁寧に進めることが成功の鍵となります。そのためには、問題行動の正確な記録、明確な指導内容、そして一貫した対応が不可欠です。
また、法的リスクを回避し、適切な手続きを踏むためには、社会保険労務士などの専門家の知見を活用することが非常に有効です。適切な改善指導を通じて、社員の成長を支援し、企業の持続的な発展に繋げていきましょう。
- 問題社員対応に関するお悩みをお持ちの方はこちらから

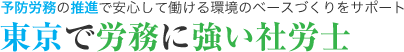

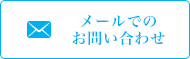

 セキュリティ体制
セキュリティ体制